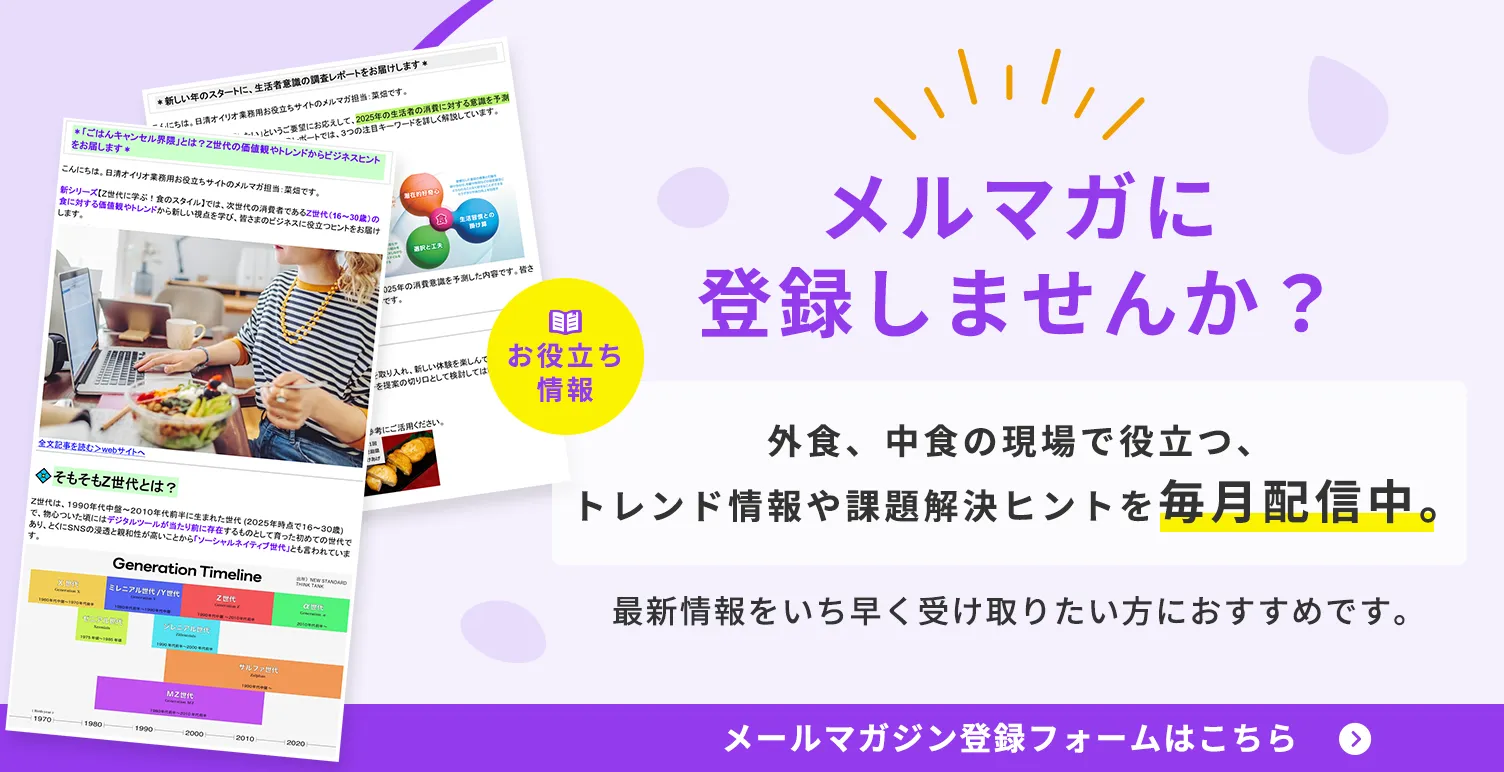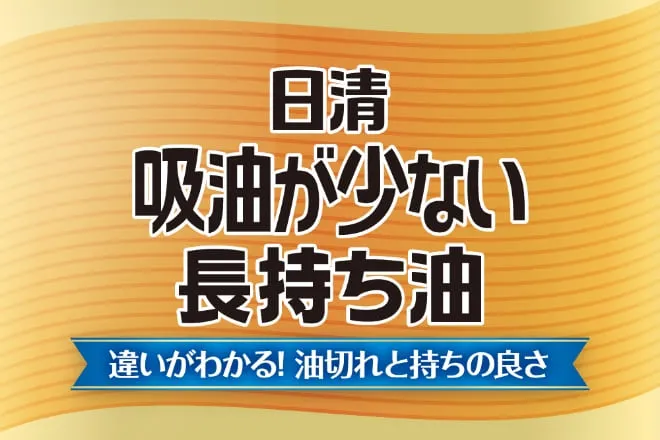飲食業界の今後は?これからの飲食店の生き残り術
公開日:2023.12.15
更新日:2025.10.24

0年以降のコロナ禍を経て、飲食業界は大きな転換点を迎えています。需要回復の兆しが見える一方で、2030年に向けてより深刻な課題が待ち受けているのも事実です。変化に柔軟に対応し、効率化を意識した経営戦略が求められる今、どのような飲食店が生き残るのでしょうか。
本記事では、飲食業界が直面する今後の課題や対策、そして成長のための最新トレンドについて詳しく解説します。
目次
飲食業界が直面する今後の課題
2030年問題とは何か?
飲食業界において「2030年問題」とは、2030年頃をピークに日本が直面する複合的な社会課題を指します。少子高齢化がさらに進行し、労働人口の大幅な減少と高齢者人口の急増が同時に起こることで、飲食業界にも深刻な影響を与えると予想されています。
具体的には、15~64歳の生産年齢人口が2030年には約6,700万人まで減少し、2020年と比較して約800万人も減少する見込みです。この労働力不足は、特に人材依存度の高い飲食業界にとって、致命的な打撃となる可能性があります。
現在、すでに飲食店の5割以上が人手不足を実感しており、2030年に向けてこの問題はさらに深刻化すると見込まれています。高齢者の増加に伴い社会保障費の膨張が進む中、消費者の可処分所得の減少や外食需要の変化も懸念されます。こうした複数の要因が重なることで、飲食店の経営環境は今後さらに厳しさを増すことが予想されます。
参考:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)」
コスト上昇と利益への影響
電気やガス・食品・物流など飲食店経営に関わるさまざまなコストが高騰しています。株式会社シンクロ・フードが飲食店経営者・運営者向けに実施した調査では、「原材料費の高騰は貴店の営業に影響していますか?」という問いに対し、90%以上が「影響している」または「やや影響している」と回答しています。
主なコスト上昇要因としては、以下が挙げられます。
- エネルギーコスト:電気・ガス料金の大幅値上げ
- 食材費:原材料価格の高騰、円安の影響
- 物流費:燃料費上昇、ドライバー不足による配送コスト増
- 人件費:人手不足による賃金上昇圧力
- 設備投資:感染対策、DX対応による追加投資
これらの要因により、多くの飲食店が経営の舵取りに苦慮している現状がうかがえます。
利益を確保するためには、コスト管理の徹底と収益性向上の両面からのアプローチが不可欠です。
参考:株式会社シンクロ・フード「原材料の価格高騰についてアンケート調査」
消費者ニーズの変化
消費者のニーズやお店の選び方も変化しています。「安くて美味しい」だけではなく、非日常感や写真映えなど、体験価値も重視されています。
また、SNSや口コミの影響力が飛躍的に高まっており、店舗経営に与える影響も無視できないものとなっています。
こうした多様化するニーズに対応できない飲食店は、たとえコストや人手といった供給側の問題を解決できたとしても、他店との差別化が難しくなるリスクが高まります。
しかし一方で、これらの変化をいち早く捉えて柔軟に対応できる店舗にとっては、新たなビジネスチャンスを創出する大きな可能性があります。
今後を見すえた飲食店の生き残り術
今後飲食店が生き残るためにすべき対策を考えていきましょう。
人手不足への対応
少子高齢化の影響による慢性的な労働力不足の中、人材確保は容易ではありません。新たな人材確保に向けた取り組みのほか、人手不足を補うために、以下のような施策を組み合わせて行う必要があります。
レイアウト改善
限られた人員で効率的に動くために、スタッフが最小限の動きで作業できるよう、また動線上でお互い邪魔にならないよう、レイアウトを最適化し作業の時間短縮を目指します。
レイアウト改善については以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
レストランの厨房レイアウトで作業効率アップ!スムーズな動線のポイントを解説
IT・デジタルの活用
IT・デジタルの活用も有効です。例としては、事前予約や受付番号の発行などをオンライン上で管理できる順番待ちシステムや予約システム、タブレットやスマートフォンからオーダーできるセルフオーダーシステム、セルフレジ、電子マネー決済などがあげられます。
調理オペレーションの効率化
調理オペレーションの効率化も人手不足対策になります。必要な食材を取り出す、洗う、切る、加熱する、お皿を取り出して盛り付ける、洗うといった一連の工程をシミュレーションし、作業を効率化できるアイテムを導入することも有効です。また、付け合わせや副菜を作り置きができるものにすると、忙しい時間の作業量を減らすことができます。
調理オペレーションの効率化については、次の記事も参考になります。
オペレーションをどう見直す?テイクアウト・デリバリーに対応するためのポイント
コスト対策
あらゆるコストが上がり続けている中だからこそ、可能な範囲で削減を図りたいものです。飲食店のコスト対策では、まずは、飲食店においてコストの大きな比率を占めるFLコストの適正化が重要なポイントとなります。FLコストの主な削減策は、以下のとおりです。
Food cost(食材費)
食材費を抑えるには、過剰仕入れなどで出る、食品ロスをできる限り抑えることが重要です。在庫管理を徹底し、食品ロス削減を図ります。また、原価率の低いメニューを増やすことも有効です。原価率の低いメニューについて詳しくは、以下をご覧ください。
原価率の低いメニューとは?メニュー例と検討する際の注意点も紹介
Labor cost(人件費)
まずは適切なシフト管理が重要です。曜日や時間帯、天気などから予測される来店者数を考慮し過不足のないシフトを組みます。また、業務効率化を進め、限られた人数でも十分回していける体制を整えるのも効果的です。
FLコスト対策は以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
飲食店のFLコストとは?FL比率の適正値やコントロール方法などを解説
テイクアウト・デリバリーの継続
コロナ禍で広く受け入れられたデリバリーの市場規模は、成長の勢いは一服したとはいえ、コロナ禍の2倍近い市場規模を維持しているなど、安定した需要があります。
一方でテイクアウト・デリバリーには、店内提供とは異なる課題もあります。
店内で提供する料理と比べて食べるまでに時間が空くため、おいしさや見た目を保つのが難しいといったことが代表的な課題です。時間が経っても劣化しにくいメニューに絞る、メニューに合った容器を選定するなど、さまざまな工夫が必要です。
課題を知って適切に対策を講じることが、テイクアウト・デリバリーを継続し、店の収益につなげるポイントになります。テイクアウトやデリバリーの課題と解決策については、以下の記事もご覧ください。
テイクアウトやデリバリー開始に許可は必要?必要なケースや注意点などを紹介
テイクアウトメニューの課題―おいしさを保つためのポイントとは?
テイクアウト・デリバリーの課題解決策のひとつに、パスタや中華そばなど麺のほぐれやツヤ・食感を維持する麺さばき油や、ご飯のおいしさを長持ちさせる炊飯油の利用も有効です。アフターコロナで復活してきたビュッフェスタイルでもおいしさを保つのに役立ちます。この機会に、ぜひご検討ください。
麺さばき油「日清麺がほぐれやすいオイル」
炊飯油「日清炊飯油お店のごはん用」
消費者ニーズへの対応
消費者のニーズはこれまで以上に多様化しています。価格や味だけでなく、健康志向、アレルギー対応、サステナビリティ、時短、非日常性、地域性などが来店動機を左右します。大切なのは、すべてに対応しようとするのではなく、自店の強みと親和性の高い要素を選び、メニュー・提供方法・情報発信まで一貫して組み込むことです。小さく試し、反応を見て、素早く改善していく運用が差別化の近道となります。
これから伸びる飲食店の特徴やトレンドについては、次の章で詳しくご紹介します。
これから伸びる飲食店の特徴・トレンド

サステナビリティ・健康志向
消費者の価値観変化に対応した新しい飲食店のあり方が注目されています。特に若い世代を中心に、環境や健康への意識が高まっており、これらに配慮した店舗運営が競争優位につながります。
サステナビリティ経営の例
- 地産地消による CO2削減
- 食品ロス削減の取り組み
- リサイクル・リユース容器の使用
- 環境負荷の少ない調理法の採用
健康志向メニューの充実
- オーガニック食材の使用
- グルテンフリーやヴィーガンメニューの導入
- 栄養バランスを考慮したメニュー設計
- カロリー・栄養成分の明示
体験型・高付加価値・会員制など新業態への転換
従来の単なる食事提供から、体験価値を重視したビジネスモデルへの転換が成功の鍵となっています。
体験型飲食店の例
- オープンキッチン、ライブクッキング
- 料理教室併設型レストラン
- エンターテイメント要素の導入
- 季節やイベントに連動した特別体験
高付加価値サービス
- シェフのストーリーや食材の背景説明
- ペアリングサービス(料理×ドリンク)
- カスタマイズメニューの提供
- プレミアム食材の使用
会員制・コミュニティ型
- 常連客向けの特別サービス
- 会員限定イベントの開催
- 顧客同士の交流促進
- ポイントプログラムの充実
インバウンド・観光需要の復活と対応
インバウンド需要は、円安の影響もあって一人当たりの消費額がコロナ前を上回っています。さらに、2024年を通じて訪日外国人旅行者数は力強い回復を見せ、年間で3,687万人(2019年比約500万人増)の過去最高を記録しました。2025年に入ってからもこの成長は続いており、飲食業界にとって大きな追い風となっています。
今後は、こうしたインバウンド対応や観光需要の取り込みが、飲食店の成長を左右する大きなポイントとなるでしょう。
インバウンド対応策
- 多言語メニュー・スタッフ対応
- キャッシュレス決済の充実
- 日本文化体験要素の組み込み
- ハラール、ヴィーガン対応メニューの提供
観光需要の獲得策
- 地域特産品を活用した限定メニュー
- 観光マップや観光バスルートへの掲載推進
- 宿泊施設との連携強化
- SNS映えする店舗・メニュー作り
変化に対応できる柔軟性と効率化への意識を持とう
飲食業界は今、大きな変革期を迎えています。2030年問題という構造的課題と、コスト上昇、人手不足という現実的な問題が同時に押し寄せる中で、従来通りの経営では生き残ることは困難になりつつあります。
しかし、これらの課題は同時に新たなビジネスチャンスでもあります。DXによる効率化、多様な人材活用、サステナビリティへの取り組み、体験価値の創造など、変化に対応できる店舗こそが、今後の市場で優位に立てるはずです。
経営を安定、そして存続させるためには、変化に対応できる柔軟な考え方とコスト削減や作業の効率化などがポイントとなります。自店の運営をより良好な状態にするための取り組みへの積極的な姿勢こそが、これからの飲食店経営には必要ではないでしょうか。