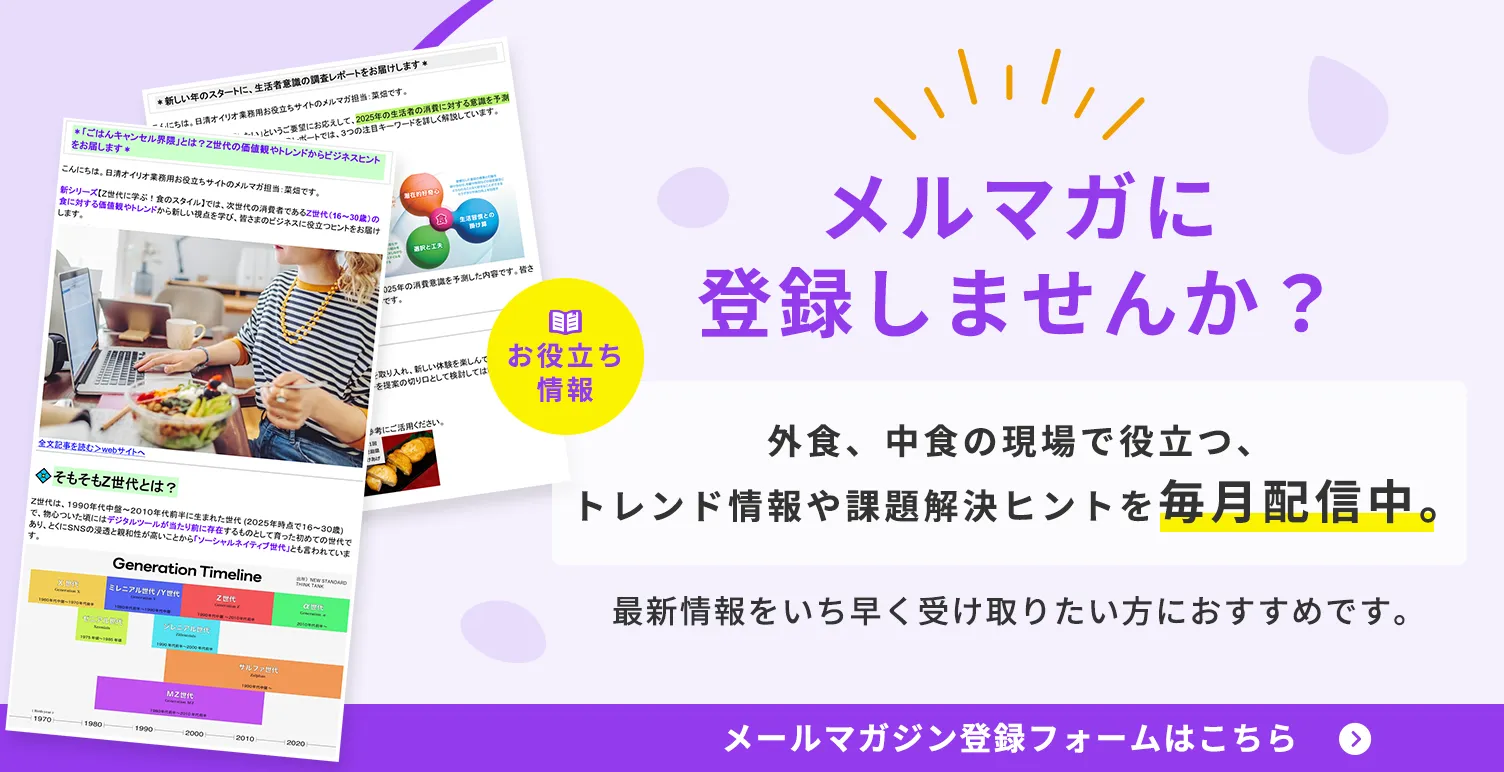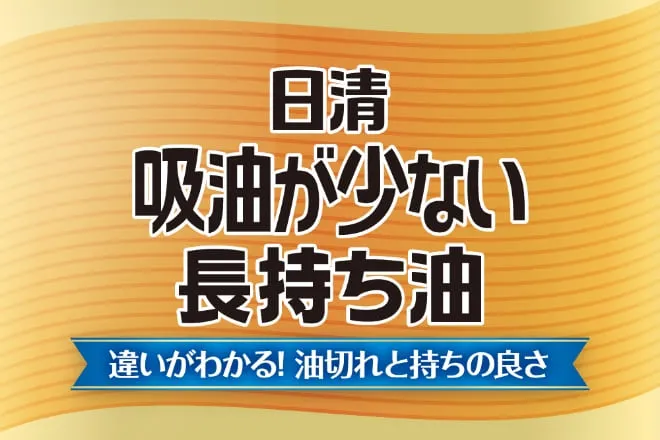メニュー開発を成功させる飲食店経営のポイントと実践プロセス
公開日:2023.06.08
更新日:2025.09.25

飲食店にとってメニュー開発は、集客と売上を左右する重要な取り組みです。実際に「メニューの魅力が来店の決め手になる」と答えるお客様も多く、メニューやその見せ方が新規顧客への有効なアプローチにつながることが考えられます。一方で、開発には時間やコストがかかり、思うような成果につながらないと悩む店舗も少なくありません。
本記事では、飲食店がメニュー開発を成功させるための実践プロセスとポイントを整理し、さらに行き詰まったときに役立つヒントをご紹介します。
目次
飲食店のメニュー開発のプロセス
飲食店が新メニューを開発する際の一般的な流れを5つのステップでご紹介します。その前に、まずメニュー開発の意義を確認しましょう。
メニュー開発の意義
メニュー開発は、新規のお客さまの獲得と今までの常連のお客さまを手放さないために行う取り組みです。
従来のメニューだけでは惹きつけられなかったお客さまを新しい固定客にして経営を維持するために、新しいメニューの開発は必要です。一方で、「このお店のこのメニューが良い」という理由でお店に通い続けてくださる常連のお客さまがいます。そのため、彼らが継続して通いたくなるよう、従来のメニューを残す必要はあります。とは言え、毎度同じメニューだけでは、リピートの頻度も限られてくるでしょう。
以上のことから、新メニューと旧メニューが併存する環境をつくることが大切です。
開発した新メニューを目当てに新規のお客さまが増え、このメニューが常連のお客さまにとってもお気に入りになれば、大きな売上アップも見込めます。
新規メニュー開発では、新規顧客層の開拓と固定客の維持の両方を視野に入れることが大切です。
メニュー開発のプロセス【5ステップ】
STEP1 市場リサーチ・顧客ニーズの調査
まず、競合店や業界のトレンド、自店の既存客のニーズを把握します。
- 最近人気のジャンルや話題の食材は何か?
- 常連のお客さまが求めているものは何か?
- 自店舗の強みや特徴は何か?
こうした情報を集めることで、「売れるメニュー」「話題になるメニュー」の方向性が見えてきます。
STEP2 コンセプト設計・ターゲットの明確化
次に、開発するメニューの「コンセプト(方向性)」を明確にします。
- お店のブランドや世界観から逸脱していないか
- ターゲットとするお客さま像に合っているか
たとえば「健康志向の女性客向け」「ランチ利用のビジネスマン向け」など、誰のためのメニューかを意識して設計しましょう。
STEP3 メニューアイデアの発案・原価計算・試作
コンセプトをもとに具体的なメニュー案を考えます。
- 食材や仕入れコスト、調理方法は現状の設備で無理なく実現できるか
- 実際に試作してみて、味・見た目・コストバランスをチェック
ここで原価率(コスト)をしっかり意識することも、利益を確保するための重要ポイントです。
STEP4 試食・評価・ブラッシュアップ
実際にスタッフや一部のお客さまに試食してもらい、味や提供方法についてフィードバックをもらいましょう。
- 味や見た目、ボリューム、調理時間はどうか
- 現場の意見やお客さまの声をもとに、レシピや盛り付けを改善
STEP5 販売開始・効果測定・改善
メニューを販売開始したら、売上データやお客さまの反応をこまめに確認します。
- 人気メニューはどれか
- 仕入れや調理オペレーションに無理はないか
- 必要に応じて価格や内容、販促方法を改善
メニュー開発は、やみくもに進めるのではなく、「調査→コンセプト設計→試作・原価計算→評価→改善」という一連の流れを丁寧に踏むことが成功への近道です。
自店の強みやお客さまの声を活かしながら、集客・利益アップにつながるメニューを生み出しましょう。
成功する新規メニュー開発のポイント
前述した「顧客ニーズを満たしているか」「店舗のコンセプトから逸脱していないか」の他にも、新規メニューを開発する際に留意すべき重要なポイントがあります。

今の設備や道具で作れるか
今の店舗設備や道具で新規開発予定のメニューを調理し、お客さまに提供できるかどうかも確認しなければなりません。新たな設備や器具の購入が必要になるのであれば、それをほかのメニューでも使用するか、コスト面で問題はないかなどを検討する必要が出てきます。
適切な提供時間を維持できるか
料理の提供に時間がかかれば、お客さまの不満につながる原因になります。また、ひとつのメニューに仕込みや調理の時間を取られれば、店舗全体の業務効率が悪くなり、回転率・売上にも影響を及ぼしかねません。誰が作っても一定レベルの質を維持したまま適切な提供時間で作れるメニューかどうかも、検討する必要があります。
調理効率化は店の回転率を上げ売上向上につながるため、積極的に実施したい取り組みです。調理効率化について詳しくは「調理効率化のポイントは?お客様満足度と回転率の向上を図るために考えるべきこと」を、回転率について詳しくは「飲食店の回転率向上で売上アップ!改善のノウハウや具体的な方法を紹介」をご覧ください。
他店との差別化ができるか
当然ですが、他店との差別化がしっかりできているメニューであれば、それを提供することで来店客数の増加が見込めます。「このお店に来店しなければ食べられないメニュー」の存在は、お客さまが来店する大きな理由になります。
他店と差別化するには、何も奇抜なアイデアが必要というわけではありません。SNSに料理の写真が掲載されることを見越して「映え」を意識した盛り付けにする、肉料理をお客さまの目の前で焼く、有機野菜を使うなど、ちょっとしたアイデアを盛り込むことでほかとは違うメニューとなります。
失敗しないための注意点とチェック項目
新規メニュー開発で失敗しないために留意しておきたい点を2つ解説します。
原価率を考慮する
飲食店の原価とは食材費です。この原価が売上高に占める割合を原価率と言い、原価率が高いと利益が下がり、原価率を抑えればその分利益が出ていることになります。そのため、できる限り原価率の低いメニューを開発したいところですが、その結果、お客さまが魅力を感じないようなメニューになっては意味がありません。
店舗経営とお客さま満足度の両立のため、原価率の低いメニューと原価率の高いメニューのバランスを考えることも大切なポイントになります。
飲食店の原価率について詳しくは、「原価率の低いメニューとは?メニュー例と検討する際の注意点も紹介」や「飲食店の原価率とは?出し方や抑える方法を解説」をご覧ください。
食材ロスを抑える
食材のロスは原価率が上がる原因のひとつです。廃棄する部分が少ないメニュー開発をすることで原価率の抑制につながります。例えば、多くの種類の食材を必要としないメニュー。使用する食材が限定され、腐ったり傷んだりする前にすべての食材を使い切ることができます。また、使用する食材の種類が少なければ、それだけ調理の手間と時間が少なく済み、調理の効率性もアップします。
食材ロスの削減は、SDGsへの取り組みとしても求められます。詳しくは、「食材廃棄を減らすためには?利益向上とSDGsに向けて食品ロス対策に取り組もう」をご覧ください。
メニュー開発に行き詰まった際のヒント
メニュー開発はアイデアが行き詰まりやすいものです。とくに日々の業務が忙しい中小外食の現場では、調理設備やオペレーションに無理なく、かつトレンドを押さえた提案を続けることが重要です。そんな時に役立つのが、「ちょい足し」や「風味油」を使った既存メニューのブラッシュアップです。
既存メニューにちょい足しでバリエーションアップ
新たな食材を大量に仕入れたり、調理工程を複雑にしたりせずとも、既存メニューに一工夫加えるだけで新しい魅力を打ち出せます。たとえば、
・カットポテトに液状のバター風味油をからめて粒マスタードと食塩を合わせる
・ポタージュの仕上げにネギ風味油を回しかけて香ばしさのなかにコクや甘さのある味に仕上げる
など、油を変える・加えるだけでも印象は大きく変わります。
これらのちょい足しは、調理オペレーションに負担をかけず、原価率や食材ロスにも配慮しやすいのが特徴です。
くわしくは「ちょい足しでバリエーション豊富なメニュー作り!既存商品に新たな発見を」をご参照ください。
ちょい足しには「日清素材のオイル」がおすすめです。
ポイントを押さえて新規メニューを開発しよう
店舗の経営を維持し、利益を上げるためには新規メニューの開発が必要不可欠です。新規メニュー開発は手間と労力がかかりますが、店舗のコンセプトから逸脱せずお客さまのニーズに応えられるメニューを生み出し続けることができれば、従来のお客さまが飽きずに足を運んでくださり、新規のお客さまの開拓も可能になります。
新規メニューを開発する際、店のコンセプトやお客さまのニーズに合っているかが重要ですが、お客さま満足度の点からも店の経営の点からも調理の効率を考慮することははずせないポイントです。
調理効率を踏まえたメニュー開発の手段として、「風味油」の活用も効果的です。
風味油は複数の調味料を使う手間が省けるだけでなく、炒める時に焦げ付きにくく、調理後の洗い物の時間短縮にもつながります。新規メニューを開発する際は、風味油の使用も積極的に検討されてはいかがでしょうか。
「日清素材のオイル」へ
これまでの油を風味油に変えるだけでも立派なメニュー開発になります。こういった「ちょい足し」でメニューを開発する方法はほかにもあります。
「ちょい足しでバリエーション豊富なメニュー作り!既存商品に新たな発見を」をご参照ください。