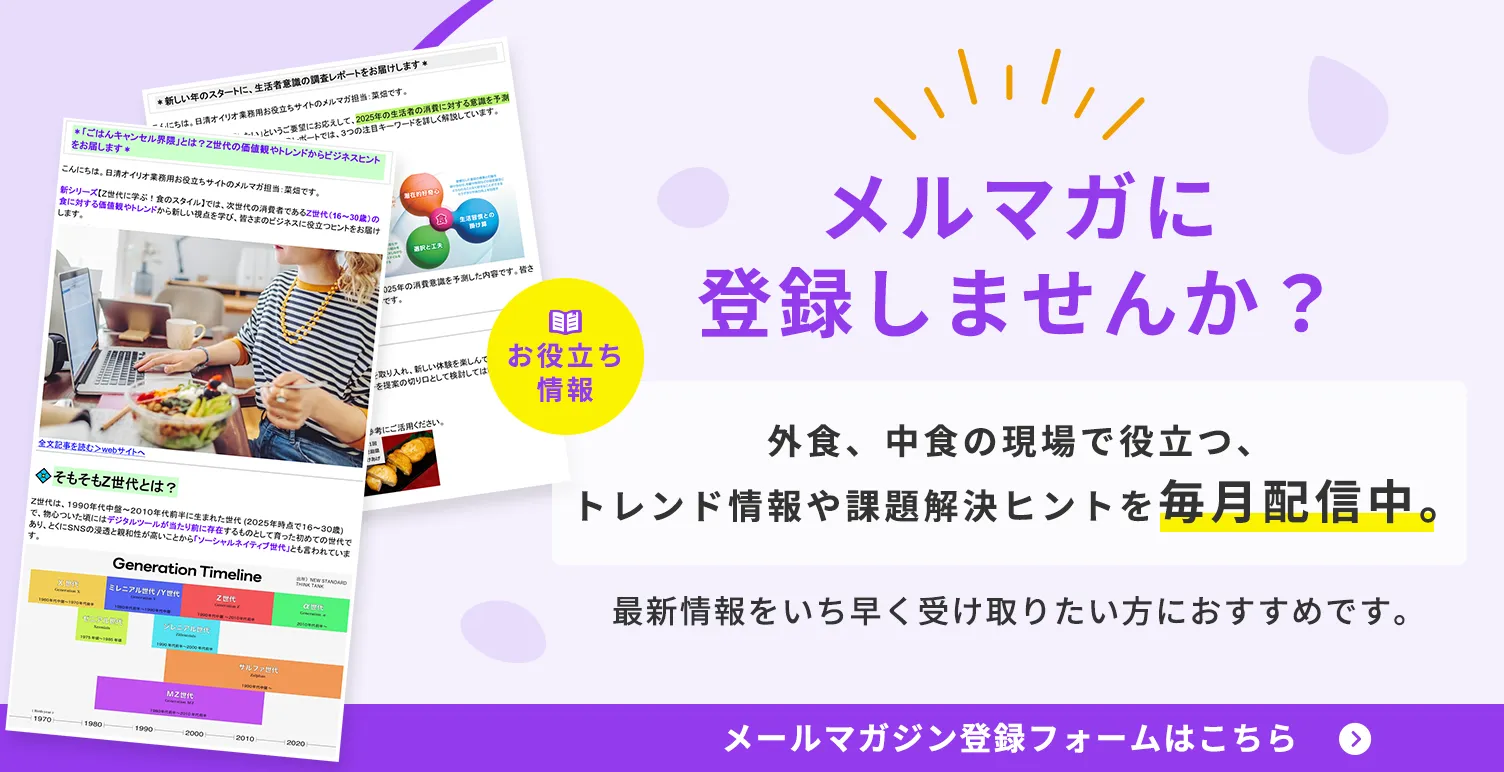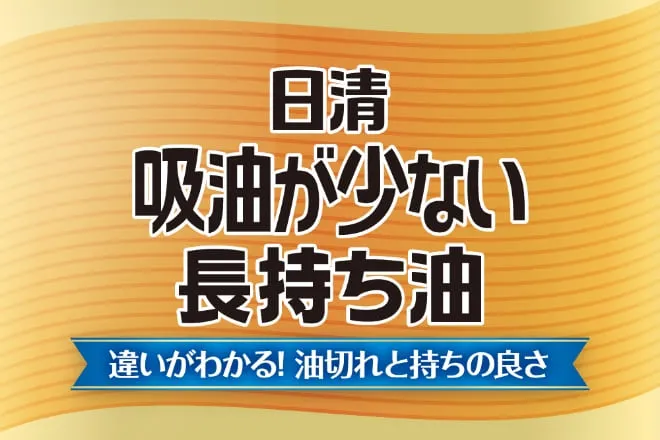フードデリバリーサービスは活用すべき?メリット・デメリットを解説
公開日:2023.11.01
更新日:2025.09.26

フードデリバリーは販路拡大に有効で、多くのお客さまに料理を提供できるという大きなメリットがありますが、自店舗で一から準備して始めるとなると、時間と手間がかかります。そのため、フードデリバリーサービスを活用する飲食店が増えてきました。
これからフードデリバリーサービスを活用してフードデリバリーを始めることを検討しているが、実はサービスの内容をよくわかっていないといった飲食店もあるでしょう。
今回は、フードデリバリーサービスの概要と、飲食店がサービスを利用する際に知っておきたいメリットとデメリットなどを解説します。
目次
フードデリバリーサービスとは?市場の現状
フードデリバリーサービスとは、PCやスマートフォンを利用して、プラットフォーム事業者がオンライン上で料理の注文を受け、配達するサービスです。
注文の取次ぎのみを行う事業者と、注文取次ぎと配達代行の両方を行う事業者が存在します。また、同じ注文・配達代行型でも、プラットフォーム事業者の自社配達員が配達を担当する形態と、個人事業者に配達を依頼する形態の2つがあります。
2025年現在の市場動向
サカーナ・ジャパンの最新データによると、2024年1月から12月までのデリバリー市場規模は7,967億円で、前年同期比7.6%減となりました。しかし、コロナ前の2019年と比べると90.5%増と、依然として大きな成長を維持しています。
外食(イートイン)の回復により一時的な減少は見られるものの、コロナ前の約2倍に近い水準を維持しており、フードデリバリーは私たちの生活に定着した新しい食事スタイルとして確立されています。
参考:<外食・中食 調査レポート> Circana, サカーナ・ジャパン調べ
利用者の変化と定着
現在のフードデリバリー利用は、コロナ禍における「外出できない時の代替手段」から大きく進化しています。利用目的で最も多いのは「料理をするのが面倒」(29.6%)ですが、「贅沢な気分を味わいたい」「家族や友人とお家時間を楽しみたい」といったプラスの体験を求める利用も多く、日常的な食事の選択肢として定着していることがわかります。
また、20~30代の利用が目立つものの、60代でも約3割が利用経験を持つなど、幅広い年代にサービスが浸透しています。これらの変化は、フードデリバリーが一時的なブームではなく、ライフスタイルの変化に根ざした継続的な需要であることを示しています。
参考:「フードデリバリーの利用状況に関する実態調査」合同会社YUM JAM
フードデリバリーサービスを活用するメリット
飲食店がフードデリバリーサービスを利用することにより、次のようなメリットが期待できます。

配送にかかる設備や人手を増やさずに、フードデリバリーを始められる
自店でフードデリバリーを実施する際には、注文の受付や配送の体制づくりが必要となります。
フードデリバリーサービスを利用すると、配送にかかる人材や設備はサービスを提供する事業者が用意してくれるため、新たに人材や配送設備などを増やすことなくフードデリバリーを始められます。
特に人手不足が深刻化している現在の飲食業界において、この手軽さは大きな魅力となっています。
新規・潜在顧客の獲得
フードデリバリーサービスを実施することで、店舗に足を運ぶことが難しい顧客を取り込むことが可能です。
中でも効果的なのは、大手フードデリバリープラットフォームの活用です。多様な店舗が集まるプラットフォームほど利用者数が多く、新たな顧客との接点を大幅に増やせると考えられます。これまで店舗の存在すら知らなかった潜在顧客にもリーチできるため、効率的な新規開拓が可能となります。
売上アップと安定した収益源の確保
フードデリバリーを活用すれば、店舗の商圏や席数・回転率に縛られず売上を拡大できます。
加えて、天候の影響を抑えて安定した売上を確保することにもつながります。店内飲食需要が減る雨天や猛暑の日は、むしろ「外食を避けたい」という層からのデリバリー需要が高まりやすいタイミングです。
フードデリバリーサービスを活用するデメリット
多くのメリットが期待される一方で、注意しなければならない点もあります。
品質の低下リスク
店舗での提供とは違い、出来立ての状態から届くまでに時間がかかるため、メニューの温度管理や品質の低下への工夫が必要となります。
配達時の温度管理は利用者の不満要因としても上位にあがっており、冷めてもおいしく食べられる工夫をする、風味が損なわれないためのメニュー開発や作り方の検討をするなどが求められます。
配達トラブル
天候や交通事情などによる遅延の発生リスクがあります。また、配達員のクオリティにばらつきがあり、遅配や盛り付けの崩れ、マナーが悪いなどの理由から、顧客の不満やクレームにつながるケースもみられます。
手数料コスト
サービスの利用には、当然手数料が発生します。一般的には、売上の15~35%程度が手数料として差し引かれます。中でも、配達代行を利用する場合は30~35%、自社配達の場合は10~15%程度が目安です。そのため、小規模な店舗や低価格帯の商品を提供する場合には、手数料コストによる利益への影響が大きくなる可能性があります。
許可取得の手続きが必要なケースがある
開業時に取得した飲食店営業許可の範囲内のメニューであれば、デリバリーで提供するために新たな許可の取得は原則不要ですが、メニューによっては新たに許可の取得が必要なケースがあります。酒類など、店舗で提供していてもデリバリーする際には注意が必要なメニューもあります。フードデリバリーサービスを利用したとしても許可の取得は店舗で行わなければなりません。取得するための手続きの手間や、時間がかかります。
許可が必要なケースについては、「テイクアウトやデリバリー開始に許可は必要?必要なケースや注意点などを紹介」をご覧ください。
フードデリバリーサービスを活用する際のポイント
フードデリバリーサービスを活用する際のポイントを紹介します。
コストと収益性のバランス
フードデリバリーへの対応のために赤字にならないよう、計画しましょう。フードデリバリーサービス事業者に支払う手数料に加えて、作業の人件費やパッケージングのコストなども考慮し、収益性を見極める必要があります。
品質維持
フードデリバリーでは、料理の品質が店内と同じように保たれることが重要です。おいしさを損ないにくいメニューの選定、調理の工夫、適切な温度管理・パッケージングなどへの配慮が必要です。
マーケティングとプロモーション
フードデリバリーサービスを利用する飲食店が多くなり、競争が激化している場合があります。選びたくなるような魅力的な画像の選定、SNSやWebサイトによる情報発信などを行い、フードデリバリープラットフォーム内での注目を集める戦略が必要です。
フードデリバリーサービスの選定
サービス提供地域や手数料など、フードデリバリーサービスによって条件は異なります。自店舗のメニューや客層、利用者数、手数料、そのほかの条件と照らし合わせて慎重に選定することが大切です。
2025年現在、フードデリバリーサービスのシェアには偏りがありますが、各サービスにはそれぞれ特色があるため、複数のプラットフォームへの出店を検討するのも有効です。
フードデリバリーサービスを活用し経営の柱を強化する
フードデリバリーの実施は新たな収入源となり、店舗での売上が伸び悩んでいる店にとっては、売上拡大への有効な手段となります。
ただし、自店舗で一から準備するとなると多大な時間と手間がかかるため、フードデリバリーサービスの利用が効率的です。まずはフードデリバリーサービスの概要を理解し、検討されてはいかがでしょうか?
なお、フードデリバリーを行うにあたっては、店舗での味と変わらないおいしさで、お客さまの手元に届くよう工夫することが重要です。冷めてもおいしいメニューに絞ったり、ご飯とおかずが完全に分けられる容器や汁物がこぼれない容器を選んだりといった対策が考えられますが、調理時においしさを保つ工夫をするのも一つの方法です。
例えば調理時に「日清麺がほぐれやすいオイル」や「日清炊飯油お店のごはん用」を使う方法があります。日清麺がほぐれやすいオイルを利用すると、麺類のツヤと食感を保つことで、時間が経過してもおいしい麺料理の提供につながります。また、炊飯油を使うと、ご飯を一粒一粒コーティングし、つやが良くふっくらとした状態が持続します。麺がほぐれやすくなったりご飯をよそいやすくなったりするメリットもあり、調理の効率化にもつながります。
ぜひご検討ください。
調理の効率化については、以下の記事で詳しく紹介しています。「調理効率化のポイントは?お客様満足度と回転率の向上を図るために考えるべきこと」